「表紙」2024年11月14日[No.2062]号
大和からきた組踊
伊江村東江上区「忠臣蔵」
区民が輝く舞台本番に密着
芸能の盛んな伊江島の中でも、東江上区だけに受け継がれる組踊「忠臣蔵」。人形浄瑠璃、歌舞伎の演目である「仮名手本忠臣蔵(かなでほんちゅうしんぐら)」を見た先人が、作り上げたとされる。先月12日に行われた「東江上区民俗芸能発表会」に合わせて島を訪れ、役者・裏方として情熱を注ぐ区民たちの姿を記録した。
組踊「忠臣蔵」のせりふは、うちなーぐち(首里言葉)が中心で、伊江島の言葉・発音も混じる。伴奏も三線を中心とした沖縄民謡だ。
シナリオは「仮名手本忠臣蔵」に沿った”仇討(あだう)ちもの“である。登場人物たちの心情の描写に重点を置くところも同様。ただし、人名は塩冶の按司(ちゅんなーぬあじ、「仮名手本忠臣蔵」における塩谷判官)、高良大按司(たからうふあじ、同・高師直)、大石大主(ういしうふぬし、同・大星由良之助)などにアレンジされている。大和の雰囲気を残しつつも、物語の舞台は琉球なのだ。
記憶でつないだ台本
大和発祥の「忠臣蔵」を島に伝えたのは、島出身の上地太郎(1806年〜没年未詳)という人物。首里の総地頭家に奉公し、大和へ上国、滞在中に「仮名手本忠臣蔵」に出合ったとされる。琉球に戻った後、この内容を組踊の台本に落とし込んだようだ。
東江上区民俗芸能保存会会長を務める大城茂さんによると、庶民の娯楽が少なかった時代は、台本は門外不出。踊り終わった後は焼却処分されたという。上演される年には、年長者たちがあらかじめ集まって、それぞれの記憶にある物語やせりふをつなぎ合わせ、台本を執筆したという。
仇討ちが主題であるが、殺生を明確に表現しないこともこの組踊の特徴だ。沖縄戦の激戦地であった島の記憶が背景にはある。戦後初めての上演となったのは1971年。この時台本を手がけた人々には「殺生はもういやだという気持ちがあったのでしょう」と大城さんが思いをはせた。
24年後も視野に
伊江村には8つの区があり、村踊りは一年ごとに交代で担う。加えて東江上区には「忠臣蔵」の他に2つの組踊の演目があり、一度の村踊りで上演するのは1演目。そのため、次回「忠臣蔵」を見ることができるのは24年後である。同じ配役で次回も上演されることはまずない。役者を経験した区民は、次回は指導者となる、と大城さんが教えてくれた。
物語の中で重要な役の一つ、加那ぐず(かなぐずぃ)を演じたのは知念牧子さん。宜野湾市出身で伊江島の言葉を使ったせりふには苦労したそうだ。出番の後、次回は裏方として組踊に関わるだろう、と展望を話した。知念さんに限らず、役者も裏方も全員が家庭や仕事を持つ人々。日常生活を過ごしながら、人生のある時点で芸能に関わり、次世代につなぐ役割も果たしている。区民のライフサイクルに溶け込み、受け継がれてきたのも組踊「忠臣蔵」の特徴なのだ。
「土の臭いがする芸能です」
取材の最後、大城さんが「忠臣蔵」のことを親しみを込めてそう表現したのが印象的だった。
(津波 典泰)
〈取材協力〉 沖縄県立芸術大学 呉屋淳子 向井大策(共に音楽文化専攻教員)
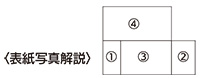
①冒頭に登場する間の者・潮平(まるむん・しゅんじゃー)。島の言葉を交えながら、物語の導入部分をこっけいに語る
②第五幕、塩冶の按司が高良大按司に切り付ける場面
③第九幕、仇討ちの計画を守るため、寺岡の比屋(てぃらうかぬひゃー)が実の妹である加那ぐずを刃にかけようとするが、大石大主が制す。基となった「仮名手本忠臣蔵」とは異なる筋書きになる場面の一つ
④第十幕、討ち入りの場面。道半ばで倒れた同志も幽霊となって参加する。天冠(てんかん)を頭に巻いた大和風の幽霊は、観客の笑いを誘う演出にもなっている

写真・津波典泰






 年
年
 月
月
 日
日