「島ネタCHOSA班」2025年03月27日[No.2080]号
八重山民謡190曲を収録した『八重山ぬ歌 工工四楽集 全巻』という本があります。編集をしたのは八重山民謡歌手・大工哲弘さん。八重山民謡の魅力が詰まった一冊なので、詳しく紹介してほしいです。
(那覇市 MA)
大工哲弘さんが手がける八重山民謡の工工四
八重山民謡の工工四ですか。三線は弾けないのですが、島々に伝わる民謡は、歴史や文化を知る手立てにもなりますよね。興味があります!
依頼のあった『八重山ぬ歌工工四楽集 全巻』の初版が発行されたのは2011年。八重山民謡歌手の大工哲弘さん(沖縄県無形文化財〈八重山古典民謡〉保持者)が、曲を工工四(くんくんしー、三線の楽譜)におこし、編さんしました。それまでは口承で伝わっており、初めて工工四をつけた、という曲もあったそうですよ。
楽集は、大工さんが歌と三線を手ほどきする県内外の教室で使用。内容のアップデートも継続的に行ってきました。先月には第3版が発売されています。編さんにかける思いを大工さんご本人に聞いてみましょう。
中舌音に工夫
「やまとんちゅーもうちなんちゅーも隔てなくさ、八重山の深淵(しんえん)なる歌を一緒に歌える。そんな日がいつか来たらなあと、ずっと願望があったんです」
そう話した大工さん。今では全国に約300人の生徒がいますが、それはキャリアを通して八重山民謡の普及に努めてきた成果です。若手だった1970年ごろは、八重山民謡の知名度はまだ低い、と感じさせられることが多かった、と教えてくれました。そんな思い出が楽集を作るモチベーションになっているそうです。
第3版の編さん作業では、約2000カ所を見直しました。特にこだわったのは八重山独特の中舌音(なかじたおん、舌の位置が「い」と「う」の中間に位置する音) の表記です。
例えば、スタンダード曲である「鷲の鳥節」。楽集内での読み仮名は「ばすぅぬとぅりぅぶす」です。これまでは工工四を書きおこした研究者や、教本ごとに表記がばらばらで、どう読めばいいか分からない、というのが初心者の悩みの種でした。今回の改訂では表記のルールを定め、直感的に発音できるように工夫しています。
「やっぱり土地の言葉と発音で歌わないと民謡じゃないからね。なまりをなくしてしまうのは、味をつけてないみそ汁みたいなものだよ」
いたずらっぽい笑みをうかべて、大工さんが教えてくれました。
ネイティブの情景
歌詞と工工四を学びつつ、歌詞の奥にある情景も感じ取ってほしいという大工さん。那覇市首里で開講している教室では、演奏の合間に言葉の解説や、八重山の歴史、幼い頃の記憶を伝えているのも印象的でした。
「ネイティブなうちなーんちゅ、ネイティブなやえやまんちゅがいなくなってるからさ。ぎりぎり僕の世代までだと思うんですよ。芋を食べて、おじいちゃんやおばあちゃんたちから言葉を教わって生活してきたっていうのは」
歌い継がれてきた曲たちを未来に残す。そんな思いも大工さんを突き動かしているそうです。楽集の後半には付録として、「月出(つくぅいで)ぬはなむぬ」、「遊(あすぅ)びとーがにすぅーざー」など の貴重な歌詞、大工さんが手がけた「とぅばらーま」の歌詞集も収録されています。歌詞を読むだけでも豊かな時間が過ごせますよ。
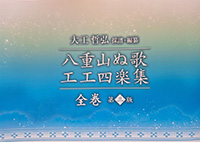
『八重山ぬ歌工工四楽集全巻』第三版
採譜・編纂・発行:大工哲弘
価格:3850円
購入のお問い合わせ:大哲会事務局(加藤)
メール:kato.daitetsukai@gmail.com
電話=080-4179-3644




 年
年
 月
月
 日
日